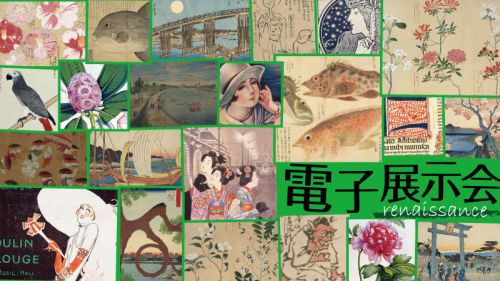鳥山石燕の妖怪図鑑でみる妖怪の世界
妖怪
鳥山石燕

『画図百鬼夜行』シリーズは江戸中期の浮世絵師、鳥山石燕の制作した妖怪図鑑です。
『画図百鬼夜行』(安永5(1776)年刊)を第1作として、『今昔画図続百鬼』(安永8年刊)、『今昔画図百鬼拾遺』(安永10年刊)、『百鬼徒然袋』(天明4(1784)年刊)が世に出ました。NDLイメージバンクにはそのうち『今昔画図続百鬼』を除く3作を収録しています。
妖怪絵は歌川国芳やその弟子の月岡芳年をはじめ、石燕の下の世代の浮世絵師によっても描かれました。ここでは石燕の妖怪図鑑を道しるべに、様々な絵師によって描かれた日本の妖怪たちを見ていきましょう。
河童
水や池にひそみ子どもや馬を水中に引き込んだり、田畑を荒らしたりと悪戯をする妖怪です。歌川広景の「江戸名所道戯尽 両国の夕立」では両国橋のたもとに落ちてしまった雷神まで川中に引きこもうとしています。
狐火
狐が灯す怪しい光、狐火です。特に大晦日の夜には関東中の狐が江戸の王子稲荷神社に集い、地元の村人は狐火の流れを見て翌年の農作の豊凶を占ったといいます。
天狗
山中に潜む妖怪とも山の神とも言われる異形です。その外見について現代では山伏のような姿で想像されることが多いですが、石燕は大きな鳥のような姿で描いています。一方、芳年の天狗はより人に近い姿をしています。
ちなみに彼は電柱の上を飛ぶ現代的な天狗たちの絵も描いています。
ろくろ首
言わずと知れた、長くのびた首が特徴的な妖怪です。石燕や豊国では女性の姿をしています。芳年の「新形三十六怪撰 おもゐつゝら」では籠の中から男性のろくろ首が登場しています。こちらは見越入道(巨大な坊主姿の妖怪)で必ずしも首の長い妖怪ではありませんが、人を見下ろすという性質から首を伸ばした姿で描かれたようです。
海座頭・海坊主
河童と同様、水の近くに出現する妖怪です。海坊主の仲間という説もあります。国芳の「東海道五十三対 桑名」は桑名の船乗り徳蔵が沖で巨大な海坊主に遭遇した場面を描いています。海坊主に「怖くないのか」と尋ねられ、徳蔵が世の中を生きていくことの方が怖いと答えると姿を消したといいます。
鬼童丸(きどうまる)
源頼光を殺害しようと、放し飼いの牛を殺してその腹の中にひそみ、待ち伏せをする鬼童丸を描いています。結局このたくらみは看破され、渡辺綱(頼光の部下「四天王」の一人)に退治されました。
源頼光と四天王による、酒呑童子や土蜘蛛退治といった武勇伝は浮世絵に頻繁に描かれました。
玉藻前(たまものまえ)・殺生石
玉藻前は金の毛の九尾の妖狐です。古代中国の皇帝や日本の鳥羽上皇を惑わし悪行を重ねるも、陰陽師の安倍泰成によって退治され、下野国那須野で殺生石となったという伝説があります。死してなお強力な毒気を発し、そばを通る鳥や獣がこれに触れるとたちまち死んでしまうといいます。
化け狸
化け狸といえば、「ぶんぶく茶釜」が有名です。茂林寺の僧侶、守鶴はいくら汲んでもお湯の尽きない不思議な釜「ぶんぶく茶釜」を愛用していましたが、実は守鶴が狸の化身であることが見破られ寺を去ってしまう、という不思議なお話です。石燕の絵では茶釜が、芳年の絵では僧侶が狸の姿をしています。
蛇女
室町時代成立の絵巻物『道成寺縁起』には若い僧に懸想した女性が、彼に裏切られたと知るや大蛇となって後を追い、道成寺の鐘の中に逃げ隠れた僧を焼き殺すという物語が描かれています。後に僧は安珍、女性は清姫と名付けられました。江戸時代には能楽や歌舞伎の題材となり、「道成寺物」と呼ばれる演目が生まれました。芳年は「和漢百物語」「新形三十六怪撰」で繰り返し清姫を描いています。
付喪神(つくもがみ)
石燕の『百器徒然袋』には日常的な生活に関わる道具が妖怪化したもの、いわゆる付喪神が登場します。これらは琵琶、琴、釜の付喪神です。NDLイメージバンクで公開中の『百鬼夜行絵巻』の写本に登場する付喪神たちと比べると、鳥山の妖怪絵が影響を受けていることが分かります。
妖怪を描いた浮世絵は多くあり、NDLイメージバンクにもたくさん収録されています。絵師ごとの描き方の共通点や違い、作品から作品への影響の仕方なども楽しむポイントの一つでしょう。
参考文献
こちらもご覧ください
妖怪
鳥山石燕