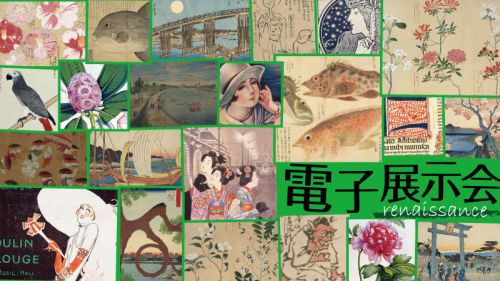あれもこれも雛人形
西澤笛畝

古今東西、雛人形は色々な型が作られてきました。ここで紹介する雛人形は、『雛百種』に収録されたもので、日本画家の西澤笛畝が古今の雛人形の優品を地方別に、また変わり雛も含めて描き紹介したものです。ここで少し紹介してみましょう。
雛人形は、上巳節に災難や厄を人の身代わり人形に托して川に流す行事と、宮中に伝わる人形遊びが結びついたことに始まるといわれています。
上の画像の人形は左から羽二重縫ぐるみの御伽這子、羽二重製の天児裸体、羽二重製の裸体天児、衣装附の天児です。這子は平安時代の小児の遊び人形で、首と胴は綿詰めの白絹、頭髪は黒髪で、這う子どもをかたどって作成されました。天児は形代の一種で、室町時代に広まり、幼児のお守りとして枕元に置きました。この這子と天児が、雛祭りが広まると天児を男雛、這子を女雛に見立ててまつるようになり、雛人形の原型となったようです。
江戸時代の雛人形
泰平の世の中になって、雛人形にも一種の型式が出現しました。寛永雛と呼ばれる雛人形もその一つです。大体は室町の雛を継承していますが、顔だちがやや長形になっています。男雛は束帯に似た装束で、両足を前に合わせています。女雛は五つ衣に似た衣装を着て冠をかぶっています。
江戸中期頃から江戸日本橋には雛市が立つようになり、享保期(1716-36)には町人が好むような人形が生まれました。面長の顔に切れ長の目、金襴や錦の華やかな装いの享保雛です。男雛は束帯に似た装束で袖を張って太刀を差しています。女雛は唐衣に似た衣装をまとっています。
宝暦期(1751-64)に生まれた有職雛は、京都の公家衆等が人形師に特別注文した人形です。公家装束を有職故実に基づいて雛に仕立てています。画像の杜園有職雛は、幕末の名工、森川杜園の木製彩色の作品です。
平安王朝時代の美女を写したような引き目鉤鼻の面差しをたたえた次郎左衛門雛です。雛屋次郎左衛門が考案したことから名づけられたといわれています。
変わり雛
菜の花雛は花を顔に見立て、菜の花を二つに折って胴体とし、松葉を差して太刀として水引を帯とする風雅な雛人形です。江戸近在で雛の季節に子どもたちが作って楽しみました。
不二雛は泥製で、富士山の形を模して造られた雛人形です。村田丹陵が彩色を施した高雅な人形です。
越か谷段雛は埼玉県越谷付近で製作された雛人形です。四、五寸(約12~15cm)の箱の中に内裏、五人囃、三人仕丁といった豆雛の人形を一まとめにして作り上げたものです。
鴻ノ巣高砂雛は埼玉県鴻巣で作られた紙製の人形です。鴻巣は人形の産地として有名でした。高砂は能「高砂」の尉と姥を表した内裏雛で、夫婦共白髪になるまで仲睦まじくという願いがこめられています。
琉球雛は、草で男女の頭を作り、紙の衣装を着せた姉様風の雛人形です。
お鏡雛は、木彫で御供物の形を作り、それに彩色を加えて三宝に乗せた人形です。画家の鳥居清忠の考案です。
夢想雛は刳物組み合わせ三段製の雛人形で、上が男雛、中が女雛、下が子どもで、一夜の夢に雛が児をもうけたということから名づけられた人形です。
土佐糸雛は古趣の変わり雛です。冠を表すような棒に紅白、黒の糸を巻き、長いほうが女雛、短いほうが男雛です。うしろの金紙の屏風様に松と鶴の泥絵風の画が描かれているのも変わっています。
ここで紹介した雛人形はほんの一部ですが、『雛百種』の中にはたくさんの雛人形が描かれています。立雛や座雛、素材も紙製、木製、土製等の様々な雛が登場します。描かれた雛人形を見ると、それぞれの地方の歴史、文化、風習等に合った人形が飾られたようです。
参考文献
西澤笛畝