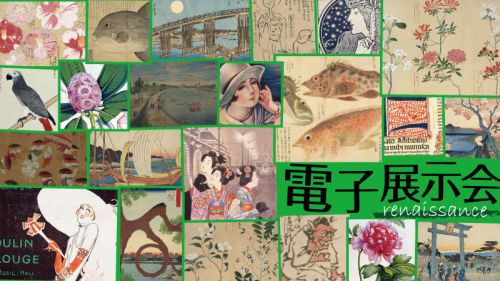蚕からの贈り物
歳時記

今も昔も、美しく上等な着物は絹製品が主流です。糸を蚕から採り、絹織物に仕立てるのは労力のいる大変な作業でした。この蚕を育てて絹糸を作る作業は養蚕と呼ばれ、5月初旬から春の養蚕が始まります。今回は江戸時代に書かれた養蚕書『画本宝能縷』『養蚕秘録』を中心に、その工程をご紹介しましょう。
1.孵化した蚕を飼育するための蚕座に移します。
2.餌とする桑の葉を摘み、葉を食べやすいように処理します。蚕はデリケートな生き物なので、蚕の糞や食べ残しを掃除するのも大事です。
3.繭を作ろうとする蚕を蔟と呼ばれる棚に移します。養蚕作業の中で最も大事な作業のひとつです。
4.糸をとるために、熱湯の中で繭を煮ながら糸繰りを行います。糸繰りした生糸を小枠から大枠にまき直します。
5.最後に生糸を機織り機で反物として織り、出荷します。
養蚕から反物ができるまでを簡単にご紹介しました。生糸を吐き出す蚕は、卵から生まれて繭になるまでおよそ1か月余りの生き物です。養蚕に携わる人々は、養蚕の成功と蚕の供養のため神仏に加護を求めました。下の画像では養蚕をつかさどる神とされる和久産巣日尊が頭の上に桑の葉を乗せて描かれています。
明治時代に入ると明治政府の蚕糸業奨励を背景に、蚕糸業は日本の主要な産業となりました。小学校等で使用された『教草』にも、養蚕の飼育の仕方を図と文で示した「養蚕一覧」や「生糸一覧」が詳しく載っています。
参考文献
こちらもご覧ください
歳時記