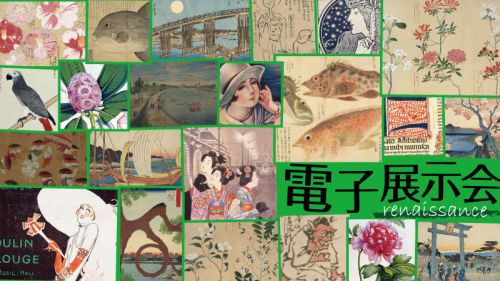堀切の花菖蒲
歳時記

初夏の到来を告げる花である花菖蒲には江戸・肥後・伊勢種の3つの系統がありますが、ここでは江戸種の代表的な名所である堀切の花菖蒲についてご紹介します。
江戸時代には、武士や町民の花への関心が高く、園芸が発達しました。花菖蒲は江戸後期に自らを菖翁と称した旗本・松平定朝が、60余年にわたり改良と新品種の作出に情熱を傾け発展させました。江戸幕府の葛西領に属する堀切では、江戸の需要を賄うための野菜と花卉の栽培が盛んに行われました。花菖蒲の栽培は19世紀初頭の享和・文化年間の頃(1801-1818)に本格化したようです。堀切村の百姓・小高伊左衛門が花菖蒲の栽培に興味を持ち、菖翁や彼の知人から品種をもらい受け繁殖させました。
小高家が花菖蒲の栽培に力を注ぎ、天保年間(1830-1843)には堀切は花菖蒲の名所として知られるようになり、多くの錦絵や名所図会に描かれるようになりました。
明治時代に入ると、明治4(1871)年にドイツ、10年にアメリカから注文があり、花菖蒲の株を輸出するようになります。23年には横山植林株式会社ができ、外国向けのカタログが作られて花菖蒲が紹介され、堀切の菖蒲はHorikiri Tokyoの名で世界の人々に知られるようになりました。堀切周辺の菖蒲園は、小高園、武蔵園に加えて、明治に入って吉野園、観花園、堀切園ができて全盛期を迎えます。
しかし、第一次世界大戦により、花菖蒲の株の輸出は大打撃をこうむり、東京の都市化等の環境変化もあり菖蒲園は衰退して次々と閉園しました。
昭和28(1953)年に、堀切園が昔の3分の1程の規模で再開し、昭和52(1977)年には堀切菖蒲園として葛飾区の文化財に指定されています。
関連電子展示会
参考文献
こちらもご覧ください
歳時記