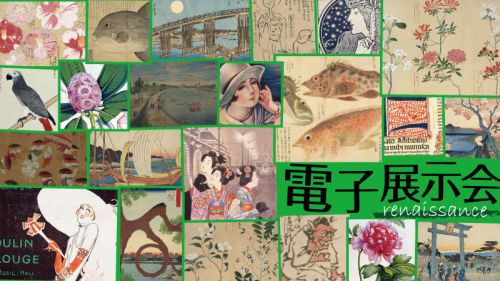西洋知識の受容と近代化
ベストセラーになった翻訳書
知識を世界に求めて―明治維新前後の翻訳事情―
明治初期のベストセラーとして特に名が挙がる「明治の三書」と呼ばれる本があります。福澤諭吉の『西洋事情』(慶応2(1866)~明治3(1870)年)、中村正直の『西国立志編』(明治4(1871)年)、内田正雄の『輿地誌略』(明治4~13(1880)年)です。
福澤の『西洋事情』は当時の西洋の状況を幅広く紹介するものであり、一部に翻訳が含まれています。中村の『西国立志編』は西洋思想書の翻訳書です。内田の著書は外国の地理書などをもとに執筆されたものであり、学校の地理の教科書として用いられました。
明治初期のベストセラーの多くが西洋の状況や文化を紹介する啓蒙書であったという事実は、外国との交流が本格化し、文明開化が盛んに叫ばれた時代状況をほうふつとさせます。
西洋事情 初編巻之1 外編巻之1
福澤諭吉は、幕末期に2度のアメリカ渡航、そしてヨーロッパ渡航を経験しており、当時としては有数の海外通だった。本書は初編3冊、外編3冊、2編4冊から成り、慶応2(1866)年に初版が出版された初編には、自ら翻訳したアメリカ独立宣言(1776年)が掲載されている。この初編のみでは読者に西洋について理解してもらうには不十分と考えた福澤は、イギリス人チェンバーズのPolitical Economyを翻訳した外編を出版した。
西国立志編:原名 自助論 第1編
西国立志編:仮名読改正 第1編
「天は自ら助くる者を助く」の有名な格言で始まる本書は、イギリスの著作家サミュエル・スマイルズのSelf-helpの翻訳。その内容は、アダム・スミスやニュートンなど、歴史上の人物の格言や成功談を紹介するものであり、立身出世の手引書として広く読まれた。中村正直(敬宇)の漢文の素養が反映され、漢字カタカナ交じりの威厳を感じさせる文体で書かれている。後に、より読みやすく書き直された『西国立志編:仮名読改正』が出版されたことは、本書へのニーズの高さを示していると言えよう。
輿地誌略
関連人物
電子展示会「近代日本人の肖像」にリンクします。
実際の展示資料
- 58. Political economy
- W. & R. Chambers Political economy for use in schools and for private instruction (Chamber's educational course) W. & R. Chambers 1876【蘭-3594】
- 59. 西洋事情 初編巻之1 外編巻之1
- 福澤諭吉 纂 岡田屋嘉七等 明治3(1870)~5(1872)年【290-H826s2】
- 60. Self-help with illustrations of character, conduct, and perseverance
- Samuel Smiles Z. P. Maruya 1885【特48-82】
- 61. 西国立志編:原名 自助論 第1編
- 斯邁爾斯(スマイルス) 著・中村正直 訳 須原屋茂兵衛 明治3(1870)年【9-33ロ】
- 62. 西国立志編:仮名読改正 第1編
- 斯邁爾斯 (スマイルス) 原著・中村正直 原訳・中村秋香 和解 有終堂 明治15(1882)年【特35-434】
- (参考)輿地誌略
- 内田正雄 内藤傳右衛門 明治6(1873)年【Y994-L1600】