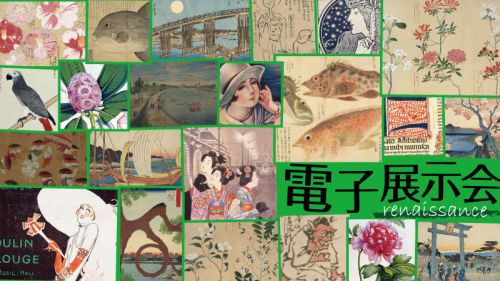近代法制の整備と明治憲法の制定
知識を世界に求めて―明治維新前後の翻訳事情―
近代法制の整備
明治政府は、西洋諸国との対等な関係を求め、国内諸制度の近代化を進めました。幕末に結ばれた日本側に不利な内容を含む不平等条約の改正が大きな動機となり、近代法制の整備を急ぐこととなります。
政府の命によって箕作麟祥がフランスの主要な法律を翻訳し、多くの法律用語を我が国に定着させるとともに、六つの主要な法典を指す「六法」の概念を初めて紹介しました。また、フランス人の政府法律顧問ボアソナードは、箕作ら日本人委員とともに、旧刑法や治罪法(刑事訴訟法)、旧民法の起草に従事しました。
仏蘭西法律書
箕作麟祥が、参議である副島種臣の指示によって明治2(1869)年から始めたフランス法典Les codes françaisの翻訳は、明治7(1874)年にかけて『仏蘭西法律書』として刊行されていった。刑法、民法、憲法、訴訟法(民事訴訟法)、商法、そして治罪法(刑事訴訟法)が訳出され、この六つの基本法典が現在のいわゆる「六法」という用語の源流となったと言われる。また、麟祥はこの翻訳の過程で、フランス法の諸概念に対し「権利」や「義務」という漢語をあてて現在の意味で用いるとともに、「動産」や「不動産」といった新しい造語も使用した。
『仏蘭西法律書』の刊行は、明治初期の我が国にとって西洋近代法の体系の理解に大きく寄与したと言える。初訳本完成後の明治8(1875)年には校正版が刊行され、さらに明治16(1883)年には、フランスの法律家リビエールが編纂したCodes français et lois usuellesを底本として増訂版が刊行された。
明治憲法の制定
いわゆる「明治14年の政変」の際に発せられた「国会開設の勅諭」によって、明治23(1890)年を期して国会を開設することとなり、政府による憲法制定に向けた作業が本格的に始まります。イギリス流の立憲主義ではなく、君主権の強大なプロイセン(現在のドイツ)の憲法に範をとることなどの流れが定まっていき、従来からのフランス法や英米法に加えて、ドイツ法の翻訳書が増えていきます。
明治15(1882)年からの伊藤博文らによるヨーロッパ憲法調査の成果を踏まえ、ドイツ人法学者で政府法律顧問であったロエスレルやモッセの助力を得つつ憲法草案が作成され、枢密院による審議を経て、明治22(1889)年に大日本帝国憲法が発布されました。
国権論 第2号
明治14(1881)年、品川弥二郎や西周、加藤弘之などの親独派の官僚が中心となって、ドイツ文化の移植を目的とした独逸学協会が設立される。独逸学協会はドイツの政治思想書を盛んに翻訳したが、本書もそのうちの一つ。
西哲夢物語
本書は自由民権派が刊行した秘密出版物である。伊藤博文の憲法調査におけるグナイストの憲法講義の記録のほか、プロイセン憲法の邦訳と明治憲法草案を収録している。自由民権派が、明治憲法草案の保守的な内容を世に問うために出版したとされる。
伊藤博文の一行は、近代憲法の制定に向けたヨーロッパ諸国の憲法調査などのため、明治15(1882)年3月から翌年8月にかけてヨーロッパを訪問しました。
この間に伊藤は、ベルリンでグナイスト、ウィーンでシュタインと、いずれも当時の高名な法学者にドイツ流の憲法学の講義を受けます。講義はドイツ公使青木周蔵の通訳によって行われ、秘書官の伊東巳代治が筆記で記録を作成しました。
これらの記録のうち、グナイストの講義録は長く所在が不明とされてきましたが、後年の大正デモクラシー運動を理論的に指導した吉野作造によって、それと思しき資料『西哲夢物語』が発見され、広く紹介されました。
ロエスレル氏起案日本帝国憲法草案
展示資料は、ドイツ人の政府法律顧問ロエスレルによる明治憲法草案の第1草案に位置づけられる。このロエスレル草案と井上毅作成の2案を元に、明治20(1887)年の6月から8月にかけて、伊藤博文の別荘のある神奈川県夏島で、伊藤、伊東巳代治、金子堅太郎らによって憲法草案(いわゆる「夏島草案」)が作成された。
関連する人物
電子展示会「近代日本人の肖像」にリンクします。
実際の展示資料
- 127. 国法汎論 首巻
- ヨハン・カスパルト・ブルンチュリー 著・加藤弘之 訳 文部省 明治5(1872)~7(1874)年【特56-80】
- 128. The spirit of laws. A new ed.
- Charles de Secondat Montesquieu Printed for J. Collingwood [etc. by T. C. Hansard] 1823【衆3000-0009】
- 129. 萬法精理 巻一
- 孟徳斯鳩 著・何禮之 訳 何禮之 明治8(1875)~9(1876)年【852-58】
- 130. Les codes français, conformees aux textes officiels avec la conférence des articles entre eux. Nouv. éd.
- Boucher jeune 1872【69-10】
- 131. 仏蘭西法律書 民法 巻4
- 箕作麟祥 訳 文部省 明治3(1870)~7(1874)年【CF2-3-07】
- 132. 仏国民法 六
- 【箕作阮甫・麟祥関係文書(寄託)95-3】
- 133. 増訂 仏蘭西法律書 刑法
- 箕作麟祥 訳【箕作阮甫・麟祥関係文書(寄託)101】
- 134. 仏国民法契約編講義
- ボアソナード 講義・名村泰蔵 口訳 司法省 明治12(1879)年【21-204】
- 135. 法律語彙初稿
- 司法省 編訳 司法省 明治16(1883)年【21-185】
- 136. 国権論 第2号
- シュールチヱ 著・木下周一 訳 独逸学協会 明治15(1882)年【特28-365】
- 137. 西哲夢物語
- 明治20(1887)年【特70-26】
- 138. ロエスレル氏起案日本帝国憲法草案
- 明治20(1887)年4月【伊東巳代治関係文書 書類の部2】