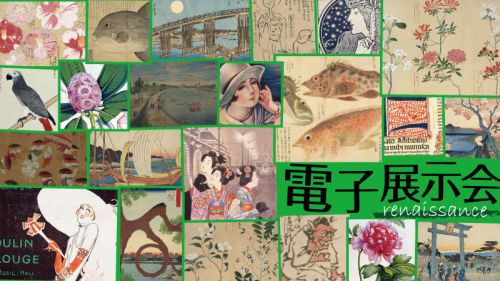江戸後期の中国白話小説の受容―『水滸伝』を中心に―
知識を世界に求めて―明治維新前後の翻訳事情―
日本人が用いてきた漢文訓読法は、必ずしも全ての中国語文献の読解に向いた手段ではありませんでした。中国語の口語で書かれた中国白話小説には訓読法を適用することが難しく、読解に一定の知識が必要とされました。それでもなお、近世日本で白話小説が流行した背景には、その多様な受容の在り方が挙げられます。
訓読法を用いて訓点や左訓(訳注)を施した訓訳本のほか、平易な日本語で書かれた翻訳書や絵本、戯作者による翻案作品が多数生まれ、漢文訓読や当時の中国で使われていた口語表現に関する知識を持たない層にも広く親しまれていました。
白話小説の影響を強く受けて誕生し、江戸後期に流行した読本は、その巧みな物語構成や格式高い文章で多くの読者を魅了しました。本節では、曲亭馬琴による読本『南総里見八犬伝』をはじめ、近世文学に特に大きな影響を与えた『水滸伝』を中心に、当時の日本で愛された白話小説の姿をご覧ください。
様々な『水滸伝』
白話小説の多くは「原書→和刻→翻訳→翻案」の順序で受容されたと言われています。まず、中国で刊行された原書を日本で刊行したものが和刻本です。和刻の際には読解の補助のため、訓点や左訓(訳注)が施されることもありました。次に、翻訳は中国語を日本語に訳したものであり、当時は「通俗」とも呼ばれました。最後の翻案は、白話小説を原作として別の作品に仕立て直すことです。平易な文章と分かりやすい舞台設定で再構成された翻案作品は、読解にそれほど知識を必要とせず、読者の裾野を広げました。
『水滸伝』もまた、原書・和刻・翻訳・翻案のそれぞれの形で享受されました。『水滸伝』の版本は全100回で構成される百回本、百回本に新たなエピソードを挿入した百二十回本、清代初期の批評家・金聖嘆が物語の後半部を削除してまとめ直した七十回本の3種に大別されます。①~③の写真は、表現に多少の異同はありますが、いずれも『水滸伝』冒頭の108の「魔君」が放たれる場面を描写した箇所です。翻案作品の『忠臣水滸伝』(展示資料148)等とも併せて見比べると、同じ『水滸伝』でもいかに多様な形で受容された
のかがお分かりになるでしょう。
①李卓吾先生批点忠義水滸伝100回 【211-544】
李卓吾先生批點忠義水滸傳100回
芥子園から刊行された百回本『水滸伝』の原書。百回本の中でも比較的新しい版。
②評論出像水滸伝4巻11回附訳文 【詩文-4022】
評論出像水滸傳4卷11回附譯文
訓訳が施された七十回本『水滸伝』の和刻。金聖嘆は七十回本を刊行するにあたり大幅に手を加えたとされる。
③通俗忠義水滸伝57巻 【231-131】
通俗忠義水滸伝 57巻
『水滸伝』の最初の和文訳。本編は百回本からの翻訳とされる。
④傾城水滸伝 【W114-N19】
傾城水滸伝 13編
曲亭馬琴による翻案作品。『水滸伝』に登場する人物の男女を逆転して書かれたもの。
実際の展示資料
- 139. 醒世恒言 40 巻
- 馮夢龍 撰 可一居士 評 墨浪主人 較 藝林衍慶堂【116-15】
- 140. 小説精言 4 巻
- 岡白駒 訳 風月堂荘左衛門 寛保 3(1743)年【W489-16】
- 141. 小説粋言 5 巻
- 奚疑主人 訳 風月堂荘左衛門 宝暦 8(1758)年【W489-15】
- 142. 英草紙 5 巻
- 近路行者 著 河内屋八兵衛 ほか 寛延 2(1749)年【211-603】
- 143. 小説字彙
- 秋水園主人 編 風月荘左衛門衣 ほか 寛政 3(1791)年【わ 813-16】
- 144. 小説字彙
- 秋水園主人 編 山口又一郎 ほか 寛政 3(1791)年【185-125】
- 145. 水滸画潜覧 3 巻
- 鳥山石燕 画 出雲寺和泉掾 安永 6(1777)年【181-143】
- 146. 繍像水滸銘々伝 初編
- 江境菴花川 編 月岡芳年 筆 小田原屋弥七 慶応3(1867)年(序刊)【W142-20】
- 147. 傾城水滸伝 13 編
- 曲亭馬琴 著 豊國(初編)・國安(2 編-12 編)・貞秀(13 編上)画 鶴屋喜右衛門 文政 11(1828)年~天保 6(1835)年【W114-N19】
- 148. 忠臣水滸伝 2 編 10 巻
- 山東京伝 作 北尾重政 画 鶴屋喜右衛門 ほか寛政 11(1799)~享和元(1801)年【190-131】